|
|
ドヴォルザーク・イン・プラハ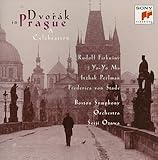 価格: 1,680円 レビュー評価:5.0 レビュー数:13
聞いていて心地よい。
こんな感じでふたりが共演してたんだって知ってよかった。
今はなかなか聞けないふたりだと思います。
決してアップをするテンポじゃないけどお勧めです。 |
「幻想」&「巨人」 小澤征爾・サイトウ・キネン・オーケストラ~ [Blu-ray] 価格: 7,140円 レビュー評価:3.5 レビュー数:2
発売直後に早速購入して数回視聴しましたが、演奏はもちろんのこと、画質、音質ともに極めて満足できる仕上がりです。特に音質面では、「幻想」の第二楽章で弦楽器パートの優秀さを大いに引き立てています。(この曲とこのオケでサントリーホールだったらさぞうかしでしょうね)他のレビューアーが指摘していたカメラ位置(2階席からのアングルが多い)については、パート毎にカメラが右往左往することがないため、かえって落ち着いた印象を受けました。蛇足ですが、「幻想」「巨人」の豪華カップリングも嬉しい限りですね。NHKには今後も豊富な放送音源(画源?)のBD化を期待したいですね。 |
武満徹 : ノヴェンバー・ステップス / ア・ストリング・アラウンド・オータム / 弦楽のためのレクエイム 他 価格: 1,800円 レビュー評価:5.0 レビュー数:4
最初に武満の音楽を聴いたとき、クラシック音楽との違いに驚いたものだ。何でこんな音楽になるのか、サッパリ分からなかったのだ。そのうちにハタと気付いた。俺の心象風景、つまりは考えの流れや感情の流れにソックリであることを。人間の意識の流れは武満的なのである。これで一気に武満の音楽が大好きになってしまった。話が脇にそれたが、武満の音楽を聴くにはこのアルバムからが最適である。武満の音楽をやらせれば、小澤征爾が一番なのだ。まさに心の盟友なのである。武満と小澤は。タケミツの代表曲ばかりが詰まっている。タケミツの世界に、ぜひ触れてみて。 |
|
|
|
|
|
交響曲第1番ハ短調 [DVD] 価格: 3,360円 レビュー評価:4.0 レビュー数:5
演奏自体は素晴らしいと思います。サイトウキネン、小澤ファンは必携の作品です。
カット割りの好みはありますが、緊迫した中にも団員同士の信頼し合ったアイコンタクトやマエストロ小澤の息づかいを映像を通して確認できる良い作品です。
ただ残念なのは、当日のアンコールが収録されていないことです。アンコールを含めたフル演奏は確か1990年頃NHK「芸術劇場」?で放映され、その時大興奮したのを思い出します。ブラームス1番の演奏が終わり、ブラヴォーの歓声の中、アンコールを求める観客が足で床を踏み鳴らす一体化したパフォーマンス!鳥肌ものなのに何故、カットされてしまったのでしょうかね?。本 |
カルミナ・ブラーナ [DVD] 価格: 3,360円 レビュー評価:3.5 レビュー数:5
こちらの演奏は1989年のジルヴェスターコンサートのもので、既発売のCDとは独唱陣が違います。特にCDのソプラノがグルベローヴァからバトルに変わっていて聴きものです。編集に多少不満がありますが、何より日本の何とアマチュア合唱団が本場の作曲家作品をドイツ語暗譜で歌いきった、大変素晴らしいドキュメントであることに価値があります。 野性味あるオケとパワー溢れる演奏はCD共々同曲の代表的な録音であることには間違いない。 |
小澤征爾大研究 価格: 2,100円 レビュー評価: 4.5 レビュー数:2 沢木耕太郎、黛敏郎、林光、レナード・バーンスタイン、島田雅彦、実相寺昭雄、石原慎太郎といった豪華な執筆陣による小澤征爾についての寄稿は、みな読みごたえがある。今は亡き優れた音楽評論家秋山邦晴と小澤とのシェーンベルク「モーゼとアロン」をめぐる対談も、秋山の歴史的文脈を常に意識した引き締まった論旨と、小澤の率直で直観的なキャラクターとの違和感がおもしろい。 それらの中でもとりわけ興味深いのは、武満徹による短い小澤征爾論である。「私は私の音楽をあれほど楽しげに演奏した指揮者を知らない。(中略)私にとっては、音楽の音たちが、私という卑小なものからときはなたれることが、いつの場合でもの |
吉田秀和・小澤征爾理想の室内オーケストラとは!―水戸室内管弦楽団での実験と成就 価格: 1,890円 レビュー評価:5.0 レビュー数:1
諸石幸生氏編による水戸室内管弦楽団の全てみたいな本。吉田秀和氏と小澤征爾氏が同楽団を作り完成させていく過程が、現実味を持って伝わってくる。とくにヨーロッパツアーのリポートは、オーケストラの演奏旅行の裏舞台が分かり面白い。吉田氏と小澤氏が日本の水戸に世界に誇れる室内オーケストラを作ろうとした(している)ことが熱く伝わってくる一冊です。
詳しいメンバー紹介や発売ディスクの紹介もあり、読み終わると全部のCDが聴きたくなる本でした。 |